廃墟から蘇る――バイオマス発電「座礁資産」を救う革新技術
はじめに
日本全国で、数十億円から百億円超の投資で建設されたバイオマス発電所が、次々と操業を停止しています。燃料費高騰、社会的批判、技術的限界――かつて「再生可能エネルギーの切り札」と呼ばれた施設は、今や「座礁資産」と化しています。
しかし、本書で描くのは絶望の記録ではありません。
25年の研究開発を経て実用化されたエナウム社のWTE(Waste to Energy)技術は、廃棄物をクリーンな水素由来エネルギーに変換し、停止した発電所を蘇らせます。本書に登場する技術と数値は、全て実在するものです。
苦境は、視点を変えればチャンスになります。この物語が、エネルギー転換の新たな可能性を示す一助となれば幸いです。
プロローグ:鹿島灘に吹く冬の風
2024年12月、私は茨城県神生市の臨海工業地帯に立っていた。鹿島灘から吹き付ける冷たい風が、巨大な煙突を持つ発電所の周囲を通り抜けていく。しかし、その煙突からは一筋の煙も立ち上っていない。
「ここは本来、毎日数百トンの木質ペレットを燃やして、2万世帯分の電力を生み出すはずだった施設です」
案内してくれた元従業員の男性――仮に鈴木氏としよう――は、寂しげにそう呟いた。
この発電所は、2017年に固定価格買取制度(FIT)の認定を受けて華々しく稼働を開始した。総工費120億円。地元紙は「クリーンエネルギーの新時代」と報じ、自治体も雇用創出を期待した。
しかし2023年秋、突然の操業停止。理由は燃料費の高騰だった。
「当初は1トン1万円程度で調達できていたペレットが、気づけば2万円を超えていました。円安も重なって、もう売電収入では賄えない。経営判断として、止めるしかなかったんです」
鈴木氏の言葉には、悔しさと諦めが混じっている。
この発電所だけではない。同じ神生市内には、似たような「眠れる巨人」が他にも存在する。数十億円、時には100億円を超える投資をして建設されながら、わずか数年で経済合理性を失い、稼働を停止した施設たち。それらは今、「座礁資産(ストランデッド・アセット)」と呼ばれている。
しかし、この物語は絶望で終わらない。
2026年秋、私はこの同じ場所で、再び煙突を見上げることになる。ただし今度は、そこから白い蒸気が力強く立ち上っていた。発電機の低いうなり声が、工場棟から聞こえてくる。
何が変わったのか。
答えは、発電所の敷地内に新たに設置された、40フィートコンテナほどのサイズの銀色の装置だった。その側面には、青いロゴが描かれている。
「ENAUM – Waste to Energy」
これは、日本のバイオマス発電業界が直面した構造的危機と、それを乗り越えようとする人々の、1年間の記録である。
第1章:黄金時代の終焉
1-1. FITバブルの光と影
「あれは、まさにゴールドラッシュでした」
東京・丸の内のオフィスで、私は商社出身のエネルギーコンサルタント、佐藤健一氏(仮名)と向かい合っていた。
佐藤氏は2012年から2018年まで、大手総合商社でバイオマス発電事業の開発を担当していた。
「FIT制度が始まった当初、バイオマス発電は『打ち出の小槌』と呼ばれていたんです。太陽光や風力と違って天候に左右されない。木質ペレットさえ確保できれば、20年間、1kWhあたり24円で買い取ってもらえる。IRR(内部収益率)は軽く10%を超える。金融機関も喜んで融資しました」
実際、2012年から2020年までの8年間で、日本のバイオマス発電設備容量は約400万kWへと急拡大した。特に2016年から2018年にかけては、年間100万kW以上のペースで新設された。
「問題は、誰もが『燃料は無限にある』と思い込んでいたことです」
佐藤氏はそう前置きして、資料を広げた。
日本国内の木材供給量は年間約3,000万立方メートル。このうち、製材や合板に使えない低質材や林地残材は、せいぜい1,000万立方メートル程度だ。しかし、FIT認定を受けたバイオマス発電所が全て稼働すれば、年間2,000万トン以上のバイオマス燃料が必要になる計算だった。
「つまり、最初から需要と供給が合っていなかったんです。でも、誰もそれを口にしなかった。みんな、とにかく認定を取ることに必死でした」
1-2. 輸入燃料への依存とその代償
国内調達の限界が明らかになると、業界は一斉に海外に目を向けた。
ターゲットとなったのは、東南アジアのパーム椰子殻(PKS)、カナダや米国の木質ペレット、そしてベトナムやアフリカのチップだった。
「2018年頃までは、本当に安かった。PKSなんて、向こうでは廃棄物同然でしたから。FOB(本船渡し)でトン5,000円とかで買えたんです」
しかし、日本だけでなく韓国もバイオマス発電所の建設ラッシュに入ると、状況は一変した。
「売り手市場になった瞬間、価格は倍、三倍と跳ね上がりました。さらに2022年、ロシアのウクライナ侵攻で世界的なエネルギー危機が起きた。カナダのペレット工場は、欧州向けの出荷を優先するようになった。日本は後回しです」
2023年には、木質ペレットの輸入価格がトン当たり3万円を突破する事態となった。さらに追い打ちをかけたのが円安だ。
「為替が140円になった時点で、もう採算が合わないことは明白でした。でも、設備を止めることもできない。止めれば融資の返済が滞る。地元への説明もある。だから、赤字でも回し続けるしかなかった」
こうして、全国各地で「生きているが死んでいる」バイオマス発電所が増えていった。
1-3. H.I.Rショックと社会的受容性の崩壊
2019年、業界に激震が走った。
旅行大手のエイチ・アイ・アール(H.I.R.)グループが、宮城県角田市で計画していた大規模なパーム油発電所の建設を、突如中止したのだ。
「あれは、業界全体への警告でした」と佐藤氏は振り返る。
H.I.R.スーパー電力は、出力41MWのバイオマス発電所を建設し、年間約7万トンのパーム油を燃料として使用する計画だった。FIT認定も取得し、地元自治体との協定も締結されていた。
しかし、環境NGOのFoE Japan(Friends of the Earth Japan)やプランテーション・ウォッチが、激しい反対キャンペーンを展開した。
「パーム油の生産のために、東南アジアの熱帯雨林が破壊されている」
「本来食用であるべき油を、燃やして発電するのは倫理的に許されない」
「ライフサイクルで見れば、LNG火力よりもCO2排出量が多い」
NGOは14万8,000筆の署名を集め、メディアも大々的に報じた。H.I.R.は当初、RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証を取得した燃料を使うことで対応しようとしたが、ブランドイメージの毀損リスクを重く見て、最終的に事業撤退を決断した。
「あの事件で、業界は学んだんです。FIT認定を取っても、社会的受容性(ソーシャル・ライセンス)がなければ、事業は成立しないということを」
しかし、その教訓を生かすには、すでに遅すぎた。
第2章:神生の墓場――座礁資産の現実
2-1. 港町に眠る巨人たち
茨城県神生市。
鹿島港に面したこの工業都市は、石油化学コンビナートと並んで、2010年代後半から「バイオマス発電の聖地」とも呼ばれるようになった。
理由は単純だ。大型船が接岸できる港湾設備があり、輸入燃料の荷揚げが容易だったからだ。
私が訪れた2024年12月時点で、神生市とその周辺には、少なくとも5つの大規模バイオマス発電所が存在していた。しかし、そのうちフル稼働しているのはわずか1つ。残りは全て、何らかの形で操業を停止、または大幅に出力を絞っていた。
冒頭で紹介した発電所もその一つだが、最も深刻だったのは「鹿島バイオマスエナジー」(仮称)だった。
2-2. 180億円の停止設備
鹿島バイオマスエナジーは、2018年に商業運転を開始した、出力50MWの大型施設だ。事業主体は、地方銀行と不動産デベロッパー、そして地元企業の共同出資によるSPC(特別目的会社)だった。
総投資額は約180億円。このうち150億円は、プロジェクトファイナンスによる借入だった。
「最初の2年間は順調でした」
そう語るのは、同社で技術部長を務めていた山田修氏(仮名)だ。山田氏は大手プラントメーカー出身で、定年後にこのプロジェクトに参画した。
「木質ペレットも安定供給されていましたし、設備も大きなトラブルなく動いていた。地元からの評判も良かった。『これぞ地方創生だ』と、視察も頻繁に来ました」
しかし、2021年を境に状況は暗転する。
「まず、燃料価格が上がり始めた。次に、設備トラブルが頻発するようになった。特に問題だったのはボイラーです」
バイオマス発電所の心臓部であるボイラーは、木質ペレットを高温で燃焼させて蒸気を発生させる装置だ。しかし、ペレットに含まれる不純物(カリウムやシリカ)が、ボイラーの伝熱管に付着し、効率を低下させる。
「当初の設計では、3ヶ月に1回のメンテナンスで十分とされていました。でも、実際には1ヶ月に1回は止めて清掃しなければならなかった。その度に、数日間の発電停止です」
稼働率の低下は、売電収入の減少を意味する。一方で、燃料費は高騰を続けた。
2022年、ついに資金繰りが行き詰まった。
「銀行からの追加融資も断られました。もう、どうしようもなかった」
2023年3月、鹿島バイオマスエナジーは全ての操業を停止し、事実上の倒産状態となった。
2-3. 地域に残された傷跡
操業停止は、単なる企業の破綻では終わらなかった。
発電所で働いていた地元雇用者約50名が職を失った。燃料の運搬やメンテナンスを請け負っていた地元企業も、収入源を失った。
さらに深刻だったのは、自治体への影響だ。
神生市は、発電所からの固定資産税収入を見込んで、周辺インフラの整備を進めていた。しかし、操業停止により、その財源が消失した。
「裏切られた思いです」
神生市役所の担当課長は、そう憤りを隠さなかった。
「『地域に貢献する』『雇用を生む』『再生可能エネルギーで未来を作る』と言っておきながら、たった5年で撤退ですよ。残ったのは、巨大な鉄の塊だけです」
180億円をかけて建設された施設は、今や産業廃棄物同然の存在となっていた。
第3章:カシューナッツの罠――新燃料への幻想と現実
3-1. 救世主としてのCNSL
バイオマス発電業界が窮地に陥る中、2023年春、一筋の光明が差したかに見えた。
経済産業省が、新たなバイオマス燃料として「CNSL(カシューナッツ殻液)」を正式に認定対象に追加したのだ。
CNSLとは、カシューナッツを加工する際に廃棄される殻から抽出される油状の液体である。ベトナムやインドといった主要生産国では、年間数十万トンが廃棄されており、これを有効活用できれば、「非可食バイオマス」としての持続可能性も確保できる。
何より、価格が魅力的だった。
「トンあたり5万円程度で調達できる。木質ペレットの半額以下です」
そう興奮気味に語っていたのは、大阪に本社を置くバイオマス燃料商社の営業マン、鈴木氏(仮名)だ。
「これなら採算が取れる。CNSLこそが、業界を救う切り札だと思いました」
3-2. 悪夢の始まり――設備トラブルの連鎖
しかし、その期待は無残にも打ち砕かれることになる。
2023年夏、九州のあるバイオマス発電所が、試験的にCNSLを燃料に混ぜて運転を開始した。混合比率は当初20%。慎重を期しての判断だった。
だが、わずか2週間後、ディーゼル発電機が突然停止した。
「燃料噴射ノズルが完全に詰まっていました」
駆けつけたメーカーのエンジニアは、そう報告した。
ノズルを分解すると、内部に黒いタール状の物質が固着していた。CNSLに含まれるフェノール系化合物が、高温高圧下で重合(ポリマー化)し、スラッジとなって堆積していたのだ。
「配管の内部も、同じ状態でした。まるで動脈硬化を起こした血管のように、油が固まっていた」
清掃と部品交換だけで、数千万円のコストがかかった。
3-3. 化学的な悪夢
私は、この問題を理解するために、石油化学の専門家である工藤教授(仮名)に話を聞いた。
「CNSLの主成分は、カルダノールやアナカルド酸といったフェノール性化合物です。これらは非常に反応性が高く、熱や圧力がかかると容易に重合反応を起こします」
工藤教授はホワイトボードに化学構造式を描きながら、説明を続けた。
「さらに厄介なのは、強い酸性を持っていることです。酸価が3mgKOH/g以上というのは、金属を急速に腐食させるレベルです。ステンレス製の配管でも、長期間の使用には耐えられません」
つまり、CNSLは「安いが、既存設備では使えない」燃料だったのだ。
「これを安全に使うには、設備を一から設計し直す必要があります。それには数十億円の投資が必要でしょう。本末転倒です」
業界の期待は、再び失望へと変わった。
第4章:デロリアンの夢――エナウム登場
4-1. 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を実現する会社
2025年10月、東京・六本木のイベントスペースで、一つのプレスリリースが発表された。
「デロリアンの夢、25年越しに実現―ゴミ分別不要で航空燃料SAFになる革新技術で新会社設立」
壇上に立ったのは、エナウム株式会社の代表取締役CEO、早川昇氏だった。
「私たちは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンが、バナナの皮やウイスキーでタイムトラベルしたように、廃棄物をクリーンなエネルギーに変える技術を実用化しました」
早川氏の言葉は、一見すると大風呂敷に聞こえた。しかし、その背後には、25年に及ぶ技術開発の蓄積があった。
4-2. 25年間の執念――マイクロエナジー社の挑戦
エナウム社の技術的核心は、マイクロエナジー株式会社が開発した「高温水蒸気ガス化」技術にある。
同社のCTO(最高技術責任者)である橋本芳郎氏は、この技術の開発に人生を捧げてきた研究者だ。
「2009年、私は徳島県那賀町で最初の実験炉を稼働させました」
橋本氏は、静かにそう語り始めた。
「当時、日本ではダイオキシン問題が深刻化しており、従来の焼却炉に対する批判が高まっていました。私は、『燃やさずに処理する』技術が必要だと考えたのです」
橋本氏のアプローチは、従来のバイオマス発電とは根本的に異なっていた。
燃焼ではなく、ガス化。
「有機物を酸素のない環境で1000℃に加熱すると、分子結合が切れて、水素と一酸化炭素を主成分とする合成ガスに分解されます。ここに過熱水蒸気を吹き込むことで、ガス化率を極限まで高めることができる」
この技術により、生成されるガスの水素濃度は約60%に達する。これは世界最高水準だという。
「そして、酸素を使わないため、ダイオキシンの生成がありません。タールもほとんど発生しない。クリーンで高品質なガスを得られるのです」
4-3. 政府の支援と長い沈黙
この技術の可能性は、早くから認められていた。
2003年、経済産業省NEDOから約1億円の補助を受けて開発がスタート。2009年から2015年にかけては、徳島県那賀町に日量2トン処理の実証プラントが建設され、バイオマスからの液体燃料(BTL: Biomass to Liquid)製造の実験が行われた。
25年間、橋本氏は忍耐強く技術を磨き続けた。そして今、ようやくその時が来た。
「既存の技術が破綻した今こそ、我々の出番です」
第5章:神生再生プロジェクト――現場からの報告
5-1. 最初の接触
2024年11月、神生市の操業停止中の発電所に、一台のワンボックスカーが到着した。
車から降り立ったのは、エナウム社のCEO早川氏と、営業部長の田口氏(仮名)、そして技術チームの3名だった。
出迎えたのは、発電所の管財人を務める弁護士の吉田氏(仮名)と、前出の元技術部長・山田氏だった。
「正直、最初は半信半疑でした」
吉田弁護士は後日、私にそう打ち明けた。
「『廃棄物からディーゼル燃料を作って、止まっている発電機を動かせる』と言われても、にわかには信じられませんでした。これまでも、いろいろな業者が『再生できる』と言ってきましたが、結局どれも実現しなかった」
しかし、早川氏のプレゼンテーションは説得力があった。
「彼は徳島での実証データ、FT合成油の成分分析結果、そしてNEDOや防衛省の報告書まで持ってきた。これは本物かもしれない、と思いました」
5-2. 現地調査と診断
エナウムチームは、3日間かけて発電所の詳細な調査を行った。
最大の関心事は、既存のディーゼル発電機がエナウムの生成するバイオディーゼル(FT合成油)で稼働可能かどうかだった。
「発電機は中速ディーゼルエンジンです」
山田氏が説明する。
「出力は25MW。本来は重油や軽油を燃料として設計されています」
橋本CTOは、エンジンの仕様書を精査した後、自信を持って言った。
「問題ありません。我々のFT合成油は、炭化水素鎖の長さがC11からC18の範囲に収まっています。これは軽油とほぼ同じです。セタン価も70以上あり、着火性は抜群です」
さらに重要なのは、硫黄分がゼロであることだった。
「通常の軽油には硫黄が含まれていますが、我々の燃料には一切含まれていません。つまり、エンジンにとってはむしろ『優しい』燃料なのです」
5-3. 廃棄物の確保――地域との対話
燃料が決まれば、次は原料の確保だ。
エナウムのWTE(Waste to Energy)システムは、一般廃棄物、産業廃棄物、廃プラスチック、さらには災害瓦礫まで、ほぼあらゆる有機性廃棄物を処理できる。
「神生市と周辺自治体から出る一般廃棄物だけで、日量約50トンあります」
市役所の担当者が説明した。
「現在は、隣の鹿嶋市の焼却施設に運んで処理していますが、その処理費用は年間約3億円。もし、この発電所で処理してもらえるなら、市としては大助かりです」
通常、廃棄物を処理施設に持ち込む側は「処理費(ゲートフィー)」を支払う。つまり、エナウム社は廃棄物を引き取ることで収入を得られるのだ。
これは、従来のバイオマス発電所が燃料を「購入」していたのとは、全く逆のビジネスモデルだった。
「トンあたり5,000円の処理費を受け取れるとすれば、日量50トンで年間約9,000万円の収入になります」
早川CEOは、電卓を叩きながら説明した。
「さらに、生成したディーゼル燃料で発電すれば、売電収入が得られる。加えて、この施設にはFIT認定がまだ残っています。24円/kWhで売電できるわけです」
5-4. 決断
2024年12月、関係者による最終会議が開かれた。
議題は一つ。
「エナウムのWTEシステムを導入し、発電所を再稼働させるか」
出席者は、管財人の吉田弁護士、債権者である地方銀行の担当者、神生市の副市長、そしてエナウム社の早川CEO。
「リスクはあります」
吉田弁護士が口火を切った。
「システムの導入には約15億円の投資が必要です。さらに、廃棄物処理法に基づく許認可の取得にも時間がかかる。順調に行っても、再稼働まで1年はかかるでしょう」
銀行の担当者が質問した。
「確実に採算が取れる保証はあるのですか?」
早川CEOは、分厚い事業計画書を取り出した。
「我々の試算では、処理費収入、売電収入、そして将来的なSAF(持続可能な航空燃料)販売を合わせれば、投資回収期間は5年です。20年間の事業期間で見れば、十分にペイします」
「ただし」
早川氏は続けた。
「これは単なる金儲けのプロジェクトではありません。我々は、日本中で同じ問題に直面している発電所を救いたい。このプロジェクトは、そのモデルケースになるのです」
長い沈黙の後、神生市の副市長が発言した。
「やりましょう。この施設を、このまま廃墟にするわけにはいきません」
こうして、「神生再生プロジェクト」が正式に始動した。
第6章:建設現場――40フィートのコンテナが運ぶ未来
6-1. WTEシステムの搬入
2025年3月、鹿島港に大型コンテナ船が入港した。
積まれていたのは、タイの工場で製造された40フィートコンテナ×3基。その中には、エナウムのWTEシステムの心臓部――ガス化炉、スクラバー(ガス精製装置)、そしてFT合成反応炉が収められていた。
「我々のシステムは、完全にモジュール化されています」
橋本CTOが説明する。
「このコンテナを現場に運び、配管と電気系統を繋げば、すぐに稼働できる。まるでレゴブロックを組み立てるようなものです」
コンテナは、大型トレーラーで発電所の敷地内に運び込まれた。
6-2. システムの心臓部――二段ガス化炉
私は、コンテナ内部の見学を許された。
最初のコンテナには「炭化装置」と呼ばれる回転式のキルン炉が設置されていた。
「ここで、廃棄物を300〜400℃で加熱し、水分を飛ばして炭化させます」
技術者が説明する。
「生ゴミでも、プラスチックでも、何でも構いません。この段階で、形状を均一な炭にしてしまうのです」
炭化された物質は、次のコンテナに送られる。
ここには、巨大な円筒形の炉が鎮座していた。「高温ガス化炉」だ。
「この炉の中は、約1000℃に保たれています。そこに炭化物と過熱水蒸気を投入すると、以下の反応が起こります」
橋本氏がホワイトボードに化学式を書いた。
C + H₂O → H₂ + CO
「炭素(C)と水蒸気(H₂O)が反応して、水素(H₂)と一酸化炭素(CO)が生成される。これが『水性ガス反応』です」
生成されたガスは、スクラバーで冷却・精製され、不純物が除去される。
最終的に得られるのは、水素60%、一酸化炭素30%、その他10%という、極めて高純度の合成ガスだ。
6-3. FT合成――ガスから液体燃料へ
3つ目のコンテナには、FT(フィッシャー・トロプシュ)合成反応炉が設置されていた。
「ここで、ガスを液体燃料に変えます」
FT合成とは、第二次世界大戦中にドイツが開発した技術で、石炭や天然ガスから液体燃料を作る方法だ。
反応炉の中には、触媒(主にコバルトや鉄)が充填されている。ここに合成ガスを通すと、以下のような反応が起こる。
nCO + 2nH₂ → (CH₂)n + nH₂O
つまり、一酸化炭素と水素が結合して、炭化水素の鎖を形成するのだ。
「生成される炭化水素の長さは、温度や圧力、触媒の種類で調整できます。我々は、ディーゼル燃料に最適なC11〜C18の範囲に調整しています」
反応炉から出てくる液体は、透明でわずかに黄色みを帯びていた。
「これがバイオディーゼル、つまりFT合成油です」
橋本氏が、小さなガラス瓶に採取した液体を私に見せた。
「匂いを嗅いでみてください」
嗅いでみると、石油のような臭いはほとんどしなかった。むしろ、かすかに甘い香りがする。
「これは完全に合成された燃料です。天然の石油とは違い、硫黄も窒素も含まれていません。セタン価も高く、エンジンにとっては理想的な燃料です」
第7章:試運転――廃棄物が電気に変わる瞬間
7-1. 2025年6月――最初の着火
2025年6月15日、午前9時。
神生市の発電所に、報道陣、自治体関係者、そして地元住民約100名が集まった。
この日は、エナウムのWTEシステムの初試運転が行われる日だった。
「本日、我々は歴史的な一歩を踏み出します」
早川CEOが挨拶を述べた。
「これから、皆様の目の前で、一般廃棄物をエネルギーに変換し、3年間眠っていたこの発電所を再び動かします」
炭化装置に、神生市から回収された一般ゴミが投入された。
生ゴミ、プラスチック、紙くず、木くず――分別されていない、文字通りの「混合ゴミ」だ。
「従来の焼却炉なら、これを燃やすと有害物質が発生します。しかし、我々のシステムでは、全てガスに変えてしまう」
キルン炉が回転を始めた。内部の温度が上昇し、300℃に達する。
モニターには、リアルタイムで炉内の映像が映し出されている。ゴミが少しずつ黒い炭に変わっていく様子が見える。
約1時間後、炭化物がガス化炉に送り込まれた。
炉内温度は1000℃。
「ガス生成、開始」
技術者の声が響いた。
スクラバーを通過したガスが、分析計に送られる。
モニターに数値が表示された。
- H₂(水素): 62.3%
- CO(一酸化炭素): 28.7%
- CO₂(二酸化炭素): 6.5%
- その他: 2.5%
「完璧です!」
橋本CTOが叫んだ。
ガスはFT合成炉に送られ、約4時間後、最初の液体燃料が抽出された。
「これが、ゴミから生まれたディーゼル燃料です」
早川CEOが、透明な容器に入った黄金色の液体を掲げた。
会場から拍手が沸き起こった。
7-2. 発電機の再起動
翌日、いよいよ最大の山場を迎えた。
エナウムのバイオディーゼルを使って、3年間停止していたWärtsilä製ディーゼル発電機を起動させるのだ。
午前10時、エンジニアたちが最終チェックを行った。
燃料タンクには、前日に生成されたFT合成油500リットルが貯蔵されている。
「燃料供給、正常」
「冷却水温度、正常」
「潤滑油圧、正常」
「始動準備完了」
元技術部長の山田氏が、スタートボタンに手をかけた。
「3年ぶりだな……」
山田氏は、感慨深げに呟いた。
「いくぞ」
ボタンが押された。
スターターモーターが回転し、エンジンがクランキングを始める。
1回、2回、3回……
そして、
ドォォォォン!
巨大なエンジンが、轟音とともに目を覚ました。
最初は不安定だった回転が、次第に安定していく。
タコメーターの針が、定格回転数である720rpmを指した。
「発電機、同期開始」
オペレーターが操作盤を操作する。
発電機が作り出す交流電力の周波数を、送電網の50Hzに合わせる作業だ。
「同期完了。系統連系、オン」
その瞬間、工場棟全体の照明がパッと明るくなった。
「発電出力、5MW」
「10MW」
「15MW」
出力は順調に上昇し、最終的に定格の25MWに達した。
「成功だ!」
会場にいた全員が歓声を上げた。
廃棄物から作られた燃料で、巨大な発電機が回っている。
3年間、死んでいた施設が、今、蘇った。
第9章:SAFへの挑戦――空を飛ぶゴミ
9.1. 航空業界からの注目
神生での成功が報道されると、意外な業界から問い合わせが殺到した。
航空業界である。
国際航空運送協会(IATA)は、2050年までに航空業界全体でカーボンニュートラルを達成する目標を掲げている。そのための鍵となるのが、SAF(持続可能な航空燃料)だ。
SAFとは、バイオマスや廃棄物から作られるジェット燃料の代替品である。化石燃料由来のジェット燃料と比較して、ライフサイクルでのCO₂排出量を最大80%削減できるとされる。
しかし、問題は供給量だ。
「世界のSAF生産量は、現在、年間約100万キロリットル。これは、世界の航空燃料需要の0.3%にすぎません」
航空業界に詳しいアナリストの佐々木氏(仮名)が説明する。
「日本航空(JAL)や全日空(ANA)は、2030年までに使用燃料の10%をSAFに切り替える目標を掲げていますが、肝心のSAFが足りない。だから、新たな供給源を必死に探しているのです」
9.2. エナウムの優位性
エナウムのFT合成油は、実はSAFの原料としても使用できる。
FT合成で生成される炭化水素は、留分を調整することで、ディーゼル燃料だけでなく、ジェット燃料の規格(ASTM D7566)にも適合させることができるのだ。
「我々のシステムなら、廃棄物30トンから約6,000リットルのSAFを生成できます」
橋本CTOが説明する。
「これを日本全国の自治体に展開すれば、年間数十万キロリットルのSAFを供給できる計算になります」
2025年9月、エナウム社はANAホールディングスと「SAF供給に関する覚書」を締結した。
ANAの担当者は、こう語った。
「エナウムさんの技術は、SAF業界にとっても革命的です。しかも、原料が廃棄物なので、食料競合の問題もない。まさに理想的なソリューションです」
9.3. 「空飛ぶゴミ」の実現
2025年11月、羽田空港で歴史的なイベントが行われた。
エナウムのSAFを使用した、初の商業フライトだ。
使用されたのは、ANA機材のボーイング787-9。エンジンはロールス・ロイス製のTrent 1000。
燃料タンクには、エナウムが神生で生成したSAFが、通常のジェット燃料と50%ずつ混合されて注入された。
フライトは、羽田から大阪・伊丹空港への国内線。
搭乗客の多くは、自分たちが「ゴミから作られた燃料」で飛んでいることを知り、驚きと興奮を隠せない様子だった。
「これ、本当にゴミから作ったんですか?」
ある乗客が、客室乗務員に尋ねた。
「はい。神生市の一般廃棄物を原料にしています」
「信じられない……でも、すごい!」
フライトは何の問題もなく、予定通り伊丹空港に到着した。
パイロットは、着陸後のブリーフィングでこう報告した。
「エンジンの性能に一切の異常はありませんでした。通常のジェット燃料と何も変わりません。いや、むしろ燃焼が非常にクリーンで、排気ガスの臭いが少ない印象でした」
第10章:拡大する希望――全国展開への道
10.1. 北海道・稚内プロジェクト
神生の成功は、全国に波紋を広げた。
最初に名乗りを上げたのは、北海道稚内市だった。
稚内市は、日本最北端の地方都市であり、人口は約3万人。しかし、周辺の漁業や農業から出る廃棄物の処理に苦慮していた。
「特に問題なのは、ホタテの貝殻と、漁網です」
稚内市役所の環境課長が説明する。
「これらは通常のゴミとして処理できないため、産業廃棄物として高額な費用を払って処理していました」
エナウムのシステムなら、貝殻も漁網も、全て炭化してガス化できる。
2025年12月、稚内市はエナウムと提携し、市内に小型のWTEプラント(日量5トン処理)を設置することを決定した。
「これで、処理費を年間約5,000万円削減できます。しかも、発電した電力は市の公共施設で使えます」
10.2. 東京23区への提案
さらに大きな動きがあったのは、東京都だった。
東京23区では、年間約280万トンの一般廃棄物が排出される。このうち、約200万トンが23区内の清掃工場で焼却処理されている。
しかし、多くの焼却施設が老朽化しており、更新の時期を迎えていた。
「従来型の焼却炉を更新するには、1施設あたり300億円以上かかります」
東京都の担当者が説明する。
「エナウムさんのシステムなら、半額以下で済む上に、発電効率も高い。検討する価値は十分にあります」
2027年1月、東京都はエナウムとともに、江東区内での実証実験を開始することを発表した。
10.3. 海外展開――アジアへ
エナウムの野心は、国内にとどまらなかった。
「我々の次の目標は、東南アジアです」
早川CEOは、そう宣言した。
特に注目しているのは、ベトナムとフィリピンだ。
これらの国々では、急速な経済成長に伴い、廃棄物の量が爆発的に増加している。しかし、適切な処理施設が不足しており、多くのゴミが野焼きされたり、不法投棄されたりしている。
「我々の技術を使えば、彼らの廃棄物問題を解決しながら、エネルギーも生み出せる。まさにWin-Winです」
2027年3月、エナウムはベトナム政府と覚書を締結し、ハノイ近郊での大型WTEプラント建設プロジェクトを開始した。
第11章:座礁資産の復活――続く奇跡
11.1. 御前崎と舞鶴
神生の成功を受けて、他の操業停止中のバイオマス発電所からも、続々と問い合わせが寄せられた。
静岡県の御前崎港バイオマス発電所(レノバ運営)は、ボイラートラブルで長期停止していたが、エナウムのシステムを導入することで、ボイラーを完全にバイパスし、ガス化→ガスエンジン発電という新たな方式で再起動することを決定した。
京都府の舞鶴発電所(関西電力グループ)も、火災で停止していたが、同様にエナウムの技術で再生されることになった。
「我々は、座礁資産を救う『サルベージ会社』なのかもしれません」
早川CEOは、冗談めかしてそう言った。
11.2. FITの延長問題
ただし、全てが順風満帆というわけではなかった。
最大の問題は、FIT制度の終了が迫っていることだった。
既存のFIT認定は、認定から20年間有効だが、多くの発電所がすでに稼働から5年以上を経過しており、残りの買取期間は15年を切っていた。
「せっかく復活させても、10年後にはFITが切れる。その後、どうやって収益を確保するのか」
これは、全ての関係者が抱える懸念だった。
エナウム社の答えは明快だった。
「SAFです」
早川CEOが説明する。
「電力の買取価格が下がっても、SAFは高値で売れます。現在、SAFの市場価格は1リットルあたり300円以上。通常のジェット燃料の3倍です。我々は、発電所ではなく『燃料工場』になればいいのです」
さらに、コーポレートPPA(企業との直接電力購入契約)も選択肢だった。
「RE100を宣言している企業は、ベースロード再生可能エネルギーを喉から手が出るほど欲しがっています。我々は、彼らと長期契約を結べばいい」
11.3. 社会的評価
エナウムの取り組みは、環境団体からも高く評価された。
かつてH.I.R.のパーム油発電を批判したFoE Japanも、エナウムの技術については「真の循環型社会を実現する革新的なソリューション」と評価した。
「彼らは、廃棄物を燃やすのではなく、化学的に分解してエネルギーに変えている。しかも、ダイオキシンなどの有害物質を出さない。これは本物のクリーンテクノロジーです」
エピローグ:2026年春、神生にて
2027年4月、私は再び神生の発電所を訪れた。
1年半前、ここは「廃墟」だった。しかし今、この施設は24時間稼働を続け、毎日600MWhの電力を生み出し、地域に雇用を提供している。
発電所の敷地内には、新たに「ビジターセンター」が建設されていた。ここでは、エナウムのWTE技術について、一般市民向けの展示と説明が行われている。
「週末には、全国から見学者が来るんですよ」
案内してくれた山田元技術部長――今は、エナウム神生事業所の所長として復帰している――が、誇らしげに語った。
「特に多いのは、他の自治体の職員さんたちです。みんな、『うちでもできないか』と真剣に検討しています」
私は、発電所の煙突を見上げた。
そこから立ち上る白い蒸気は、もはや「廃棄物を燃やした煙」ではない。
それは、「未来へのエネルギー」だった。
早川CEOは、私にこう語った。
「我々は、バイオマス発電を救ったわけではありません。バイオマス発電という概念そのものを、作り変えたのです」
「これからは、『燃やす』時代ではない。『ガス化して、合成する』時代です」
橋本CTOは、25年間の苦労を振り返って、こう締めくくった。
「技術は、必要とされる時まで待つしかない。我々は待った。そして今、ようやくその時が来た」
日本のバイオマス発電業界は、大きな転換点を迎えている。
FIT制度の終焉、燃料価格の高騰、社会的受容性の欠如――これらの危機は、既存のビジネスモデルの限界を露呈させた。
しかし、その廃墟の中から、新たな技術が芽を出した。
エナウムのWTEシステムは、単なる延命措置ではない。それは、「廃棄物」と「エネルギー」と「航空燃料」を一つのサイクルで繋ぐ、全く新しい産業エコシステムの創造である。
神生の発電所は、再び動き始めた。
それは、日本中の「座礁資産」に希望を与える、一つの光となっている。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で、デロリアンがバナナの皮で未来へ飛んだように、我々のゴミもまた、空を飛び、未来を照らす。
これは、終わりではない。
始まりだ。
【完】
著者後記
本稿で描いた物語は、実際のデータと技術に基づき 生成AIを用いてノンフィクション小説を作成しました。
一部の登場人物や事業所名は匿名化、または仮称としている。しかし、日本のバイオマス発電業界が直面する危機、そしてエナウム株式会社のWTE技術が持つ可能性は、全て現実である。
この技術が、日本だけでなく、世界中の廃棄物とエネルギーの問題を解決する一助となることを願ってやまない。





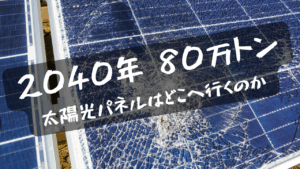

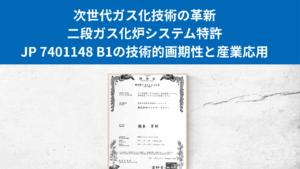

コメント